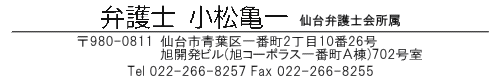| 旧TOP : ホーム > 交通事故 > 交通事故判例-脊椎脊髄関係症等 > | |
| 旧TOP : ホーム > 交通事故 > 交通事故判例-脊椎脊髄関係症等 > | |
| 令和 1年 5月13日(月):初稿 |
|
○「後遺障害等級第11級脊柱変形労働能力喪失率20%を認めた地裁判例紹介」の続きで、保険会社が労働能力喪失を否認する後遺障害第11級7号「脊柱に変形を残すもの」について、事故後、実際の減収がない場合でも、就労可能期間を通じて平均して14%の労働能力喪失を認めるべきとした平成22年7月2日名古屋地裁判決(判例時報2094号87頁)の関係部分を紹介します。 ○国税調査官(男・症状固定時31歳)の原告は、事故により後遺障害(脊柱の奇形障害11級7号該当)を残しましたが、事故後減収はなく、昇給において不利益が生じていることもありませんでした。しかし、後遺障害による派生的な症状としての腰痛のために仕事の集中力が低下していることを考慮し、税務職の職員の平均年収を基礎に、67歳までの36年間にわたり14パーセントの逸失利益が認められました。 ○「後遺障害認定後減収がない場合の逸失利益に関する判例1」でも紹介していましたが、保険会社側は、収入について現実の減収がないとのことで労働能力喪失率は多くて14%で、喪失期間は長くて5年程度であると主張していました。 ******************************************* 主 文 一 被告は、原告に対し、2380万1379円及びこれに対する平成18年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 被告は、原告に対し、3262万5268円及びこれに対する平成18年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第二 事案の概要 本件は、原告が被告に対し、被告の過失により生じた交通事故(以下「本件事故」という。)により受傷するなどの損害を被ったとして、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条の運行供用者責任により3262万5268円及びこれに対する本件事故の日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 一 前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (中略) (※原告主張) (キ)後遺障害逸失利益 2447万9628円 原告は、本件事故での受傷については、平成19年12月26日に症状が固定したが、後遺障害等級11級七号の脊柱の奇形障害が後遺障害として残った。 原告は、国税調査官であるから、逸失利益算定の基礎収入として、税務職の男女計・全年齢の推定平均年収である739万6999円とする(甲15~17)。原告の後遺障害は11級7号であり労働能力喪失率は20%である。原告の症状固定時(平成19年12月26日)の年齢は31歳であり、就労可能年数は36年(ライプニッツ係数は16・547)である。 したがって、後遺障害逸失利益の額は、739万6999円×20%×16・547=2447万9628円である。 (※被告主張) (キ)後遺障害逸失利益 平成19年12月26日に第12胸椎圧迫骨折について症状固定となったことは認めるが、後遺障害逸失利益は争う。原告は、本件事故の約1か月後の平成18年12月9日には就労を再開しており、同時点において就労可能な状態にまで回復していた。また、現時点においても税務署員として勤務しているのであるから、原告の労働能力は将来にわたって制限されていないというべきである。したがって、原告には後遺障害逸失利益は発生しない。仮に、原告の労働能力が制限されるとしても、原告の後遺障害は軽度の脊柱変形であり、可動域制限もほとんど生じていない。すなわち、労働能力に直帰する後遺障害ではない。また、自覚症状も著しい神経症状とはいえず、今後も永続的に症状が残存するとは思われない。したがって、仮に、労働能力が制限されるとしても、喪失率は多くとも14%、喪失期間は5年が相当である。 (中略) 第三 当裁判所の判断 一 争点(1)(過失相殺)について (中略) (7)後遺障害逸失利益 1713万5739円 ア(証拠省略)によれば次の事実が認められる。 (ア)原告は、本件事故により第12胸椎圧迫骨折の傷害を負い、同傷害については平成19年12月26日に症状が固定したが、後遺障害等級11級7号の脊柱の奇形障害が後遺障害として残った。また、同後遺障害による派生的な症状として、腰の上部も下部も痛く、腰が抜ける感じがするといった症状やたまに両足底がぴりぴりするといった症状がある。 (イ)原告は、国税調査官である。昭和51年7月4日生まれで、平成11年3月にCC大学経済学部経済学科を卒業し、平成11年度国税専門官採用試験に合格し、平成12年4月1日付けで大蔵事務官税務職2級(○○国税局総務部総務課)に採用され、本件事故当時は税務職の2級22号俸(固定給である俸給支給額は月額24万9300円)の給与、平成20年には税務職3級13号俸(俸給支給額27万5000円)、平成21年には税務職3級16号俸(俸給支給額28万0700円)の給与、平成22年には税務職3級19号俸(俸給支給額28万6300円)の給与を得ており、年間給与収入は平成19年(誕生日が来て31歳)が500万3732円、平成20年(同じく32歳)が531万8016円、平成21年(同じく33歳)が593万6316円である。原告は、本件事故後も、毎年3号俸ずつの普通昇給は果たしている。 (ウ)税務職俸給表の適用を受ける職員は平成19年4月1日現在で5万3157人であり、その平均年齢は42・3歳、平均経験年数は21・8年、平均給与月額は44万8303円(俸給が38万5575円、扶養手当が1万3235円、俸給の特別調整額が1万2741円、地域手当等が3万1847円、住居手当が2854円、その他が2051円)である。これは、全俸給表(職員数28万6617人、平均年齢41・4歳、平均経験年数20・2年)の平均給与月額である40万1655円よりも約11・6%高い額である。また、国家公務員の特別給(ボーナス)の年間支給月数は、平成19年が4・50月である。 イ 以上の事実を前提に、後遺障害逸失利益について検討する。 (ア)基礎年収 原告が大学を卒業し、国税専門官採用試験に合格した国家公務員の税務職の職員であるところ、平成19年の税務職の職員の平均給与月額の4・5月分を特別給と推定してその年間給与額を推計すると、その額は44万8303円×16・5=739万6999円(小数点以下切捨て)となる。この額は、平成18年の賃金センサスの企業規模計・産業計・男性・大卒・全年齢の平均賃金である676万7500円よりも9%余り高い額であるが、前記のとおり税務職の国家公務員が公務員の中で比較的高い給与を得ていることや、原告が33歳にして既に年間給与所得が593万6316円になっていることなどからすれば、原告が、生涯にわたり、平均して上記推計による年収である739万6999円を得る蓋然性は高いというべきである。 したがって、後遺障害逸失利益を算定する上での基礎年収は原告が主張する739万6999円とするのが相当である。 (イ)就労可能期間 原告は、症状固定時である平成19年12月26日において31歳であったから、就労可能期間は67歳までの36年と認めるのが相当である。 (ウ)逸失利益の有無及び喪失率 前記のとおり、原告は、本件事故後においても毎年の普通昇給を果たしている。原告本人は、同僚の中には5号俸、7号俸の昇給をしている者もいる旨の供述をする(原告本人42頁)が、そのような者がどの程度の割合で存在するのかは明らかではなく、普通昇給しかしていないという原告が、特に昇給が遅れている状況にあると認めるには足りない。したがって、現時点においては、特段本件事故による減収がないだけでなく、昇給において特段の不利益が生じているとも認めることはできない。 しかし、前記認定のとおり、原告は本件事故後、脊柱の奇形障害が残り、派生的な症状として腰痛などが残存していることが認められるところ、(証拠省略)によれば、原告は、腰痛のために仕事の集中力を欠き、能率が落ち、同僚らと比較してかなり長い時間の残業をして業務をこなしていることが認められる。 そうすると、現時点において特段の減収が認められないといっても、それは原告の努力によるところも多いというべきであるし、現時点では減収はなくても、残業によらなければ業務をこなせないことなどが、将来の昇給や昇格に影響が出る可能性は否定できない。 そうすると、原告の仕事の能率が落ちる原因が、身体の機能的な障害によるものではなく、腰痛の影響による集中力の低下にとどまることや現時点においては減収が発生していないことを考慮しても、前記の就労可能期間を通じて平均して14%の逸失利益を認めるのが相当である。 したがって、後遺障害逸失利益の額は、739万6999円×14%×16・547=1713万5739円である。 (8)後遺障害慰謝料 420万円 11級4号の後遺障害が認められるから、後遺障害慰謝料は420万円が相当である。 (9)損害額合計(弁護士費用を除く) 以上の(1)ないし(8)の合計は2373万1934円である。 (10)既払金 143万0555円 (11)損害額残額(弁護士費用を除く) 損害額合計から既払金を控除すると残額は2230万1379円である。 (12)弁護士費用 (11)の額や本件訴訟の経緯等からすれば,弁護士費用分の損害としては150万円を認めるのが相当である。 (13)したがって、損害額残額は2380万1379円となる。 三 以上によれば、原告の請求は2380万1379円及びこれに対する本件事故の日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度では理由があるから認容することとし、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。(裁判官 寺西和史) 別紙(省略) 別紙 交通事故現場見取図1、2(省略) 以上:4,241文字
|