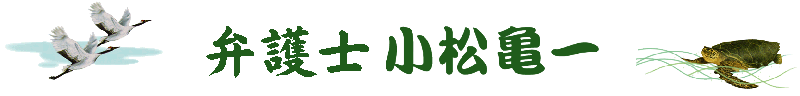○「
裁判所鑑定結果による賃料増額請求を認めた地裁判決紹介5」の続きで、建物賃貸借契約での賃料増額請求について、裁判所の鑑定結果による増額と、年1割の利息支払を命じた令和6年10月30日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。
○被告との間の建物賃貸借契約において、被告に賃料増額の意思表示をしたと主張する原告が、被告に対し、月額の賃料が増額されたことの確認を求めるとともに、増額後の差額賃料及びこれに対する借地借家法32条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求めました。
○増額が認められた賃料と実際支払賃料の差額について各弁済期から年1割の利息支払が認められます。判決主文2項で各弁済期から支払済みまで増額分との差額5万2600円に対する1割の支払を命じています。通常、利息分支払命令内容は、別紙として、うち別紙認定差額一覧表「認定差額」欄記載の各金員に対する同表「起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年1割の割合による各金員を支払えとの主文になります。
借地借家法第32条(借賃増減請求権)
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
*********************************************
主 文
1 原告と被告との間の別紙物件目録記載の建物に係る賃貸借契約について、令和5年7月6日以降の月額賃料(共益費を含む)は50万8600円(税抜)であることを確認する。
2 被告は、原告に対し、88万5716円及び
うち4万4116円に対する令和5年7月6日から、
うち5万2600円に対する令和5年8月1日から、
うち5万2600円に対する令和5年9月1日から、
うち5万2600円に対する令和5年10月1日から、
うち5万2600円に対する令和5年11月1日から、
うち5万2600円に対する令和5年12月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年1月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年2月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年3月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年4月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年5月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年6月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年7月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年8月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年9月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年10月1日から、
うち5万2600円に対する令和6年11月1日から
支払済みまで各年1割の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その1を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 原告と被告との間の別紙物件目録記載の建物に係る賃貸借契約について、令和5年7月6日時点の賃料が月額73万8548円(税込)であることを確認する。
2 被告は、原告に対し、令和5年7月6日から本件訴訟の口頭弁論終結の日の属する月まで毎月末日限り月額24万0248円及びこれに対する各該当月の1日から支払済みまで年1割の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の所有者であり、同建物を被告に賃貸している原告が、被告に対して同建物の賃料増額の意思表示をしたとして、同建物の令和5年7月6日以降の月額賃料が増額されたことの確認を求めるとともに、増額後の差額賃料及びこれに対する借地借家法32条2項所定の年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(中略)
(3)増額の意思表示
原告は、令和5年7月4日、被告に対し、本件建物の書面到達の日の翌日からの賃料を月額67万9082円、共益費を月額5万9466円(いずれも税込み)に増額する旨の意思表示が記載された書面を送付し、被告は、同月5日、同書面を受領した(甲28、29)。
(4)調停不成立
原告は、東京簡易裁判所に対し、被告を相手方として賃料増額等請求調停の申立てをしたが、同調停は、令和5年12月21日、不成立により終了した(甲31)。
(5)被告は、原告に対し、直近合意時点以降、本件口頭弁論終結時点まで、賃料月額45万3000円(税抜)、共益費3000円(税抜)を支払っている。
2 争点
本件の争点は、〔1〕直近合意が事情の変更により不相当となったといえるか、〔2〕令和5年7月6日時点(以下「鑑定時点」という。)における本件建物の適正継続賃料額、である。
(1)原告の主張
〔1〕本件建物の賃料は近傍同種の賃料と比較して著しく低廉で不相当なものとなっており、事情の変更があったといえる。
〔2〕鑑定時点における本件建物の適正継続賃料額(共益費含む・税含む)は月額73万8548円である。
(2)被告の主張
〔1〕直近合意における賃料を不相当とする事情の変更はない。
〔2〕本件建物の適正継続賃料額は現行賃料である。
第3 争点に対する判断
1 当裁判所は、本件賃貸借契約において賃料増額を相当とする事情の変更があるものと認め、また、当裁判所が実施した不動産鑑定士Cによる鑑定(以下「本件鑑定」という。)の結果を相当と認め、本件建物の鑑定時点における適正継続賃料額を月額50万8600円(税抜、共益費含む)と判断する。その理由は以下のとおりである。
(1)本件鑑定の概要
ア 結論
鑑定時点における月額実質賃料は51万4000円(税抜)であるところ、ここから適正な共益費額である月額6400円(税抜)を控除し、さらに保証金の運用益を控除した残額は50万2200円(税抜)であり、これが鑑定時点における月額支払賃料である。
イ 本件鑑定の手法
(中略)
(2)本件鑑定の合理性
ア 本件鑑定は、上記のとおり、差額配分法、利回り法、スライド法により得られた試算賃料を総合して鑑定時点における適正賃料を算定しているもので、その算定手法には合理性がある。
イ 原告の主張について
〔ア〕賃貸事例比較法を採用すべきである。
本件鑑定は賃貸事例比較法を採用していないところ、この点につき、継続の賃貸事例は極めて個別性が強く、賃料改定等の経緯の詳細な把握も困難であることから適切な比準を行うことができないとの鑑定人の意見には合理性がある。
〔イ〕本件建物の減価率89.6%は大きすぎる。
本件建物は築45年を経過しており、躯体の耐用年数は10年、仕上げ及び設備の耐用年数は3年にとどまることから、耐用年数における減価率を88.4パーセントとし、旧耐震基準による建物であること及び検査済証が交付されていないことを考慮し、観察減価率を10%と判断し、耐用年数における減価率と観察減価率を総合して減価率を89.6%としたもので、上記算定経過には合理性がある。
〔ウ〕差額配分法における賃貸人への配分は3分の1とするのではなく2分の1とすべきである。
差額配分法における配分率は、一般的要因、地域的要因に加え、対象不動産の個別性に着目して行われるところ、本件賃貸借契約において過去の賃料の増額幅が近隣地域と比較して小さいことを考慮すれば、貸主への配分を3分の1とすることには合理性がある。
〔エ〕利回り法における建物の減価率が差額配分法と異なる。
利回り法における本件建物の基礎価格は直近合意時点における建物価格を算定するためのものであり、鑑定時点の建物価格とは時点が異なり、減価率が異なることは当然である。
〔オ〕スライド法における変動率を8.2%ではなく13.3%にすべきである。
本件鑑定は、【1】消費者物価指数、【2】企業向けサービス価格指数、【3】店舗賃料トレンド、【4】全国賃料統計、【5】地価公示価格、【6】建築費指数のうち、都内の賃料変動と関連性の強い【2】、【4】を重視し、【3】を考慮した上で、変動率を8.2%としたもので、合理性がある。
〔カ〕比準賃料を重視すべきである。
原告の指摘する比準賃料(1万0600円
平方メートル)は、新規賃貸事例に基づいて算定されたものであり(本件鑑定26頁)、継続賃料を算定するに当たり重視すべきとはいえない。
ウ 被告の主張について
〔ア〕築年数が近い事例を使って期待利回りを算出すべきである。
本件鑑定は、投資用区分所有建物事例として5例を使用しているところ(本件鑑定24頁)、被告は、上記5例のうち、本件建物と築年数の近い3例のみを使用して算定すべきと主張するが、5例について、それぞれに立地や店舗面積も異なることからすれば、築年数のみに着目して3事例に限定することに合理性があるとはいえない。
〔イ〕差額配分法における貸主への配分を3分の1とするのではなく4分の1とすべきである。
差額配分法における貸主への配分を3分の1とすることに合理性があることはイ〔ウ〕記載のとおりである。差額配分法における配分対象は、本件鑑定書27頁のとおり正常実質賃料と実際実質賃料の差額であり、これを否定する被告の主張は理由がない。
〔ウ〕利回り法における遡及時点修正率は、122.1ではなく、平成30年の数値と令和5年の公示価格を使用して116.5とすべきである。
本件鑑定における遡及時点修正率は、地価公示地「台東5-19」の地価変動率(本件鑑定11頁)を基準としつつ算定されたものであるところ(本件鑑定28頁)、当該年の1月1日時点の数値である公示価格を、直近合意時(平成30年1月10日)と鑑定時(令和5年7月6日)に修正した上で変動率を算定したものと解され、令和5年の公示価格と平成30年の公示価格自体の変動率ではないのであって、これを122.1とすることには合理性がある。
〔エ〕スライド法における変動率8.2%は相当ではない。
スライド法における変動率8.2%に合理性があることはイ〔オ〕のとおりである。被告は、【1】消費者物価指数、【2】企業向けサービス価格指数、【3】店舗賃料トレンド、【4】全国賃料統計、【5】地価公示価格、【6】建築費指数のうち、特に【4】を重視すべきである旨指摘するが、本件鑑定(35頁)が重視した【2】と【4】は、いずれも本件建物の属する東京圏、東京都区部の事務所・オフィス賃料に係る統計であるにもかかわらず、数値に明確な差が生じていることからすると(【2】は+11%、【4】は+0.7%)、いずれかに比重を置くことは不相当であり、これを同等に扱うことには合理性がある。
〔オ〕差額配分法による試算賃料:利回り法による試算賃料:スライド法による試算賃料のウエイトを1:1:8にすべきである。
本件鑑定において差額配分法が重視されているのは、差額配分法においては正常実質賃料(新規賃料)と実際実質賃料との間の賃料差額が配分されているところ、正常実質賃料の査定に当たっては市場実態が反映されていることから、配分割合が適正であれば、他の2手法と比較してより適切な試算が可能であることによるものと解され、それ自体合理性がある。
他方、スライド法は、各種指数を考慮した変動率を用いるものであるが、各種指数は継続賃料の変遷を直接反映し得る性質のものではなく、これらの指数から継続賃料の変動率を適切に設定することには困難を伴うものといえ、他の2手法と比較してより重視されるべきとはいえない。
(3)直近合意を不相当とする事情の有無
本件における直近合意は平成30年1月10日に合意されたもので、鑑定時点(令和5年7月6日)まで約5年6か月が経過していること、この間、地価の変動に伴う賃料相場の変動や経済状況の変動があったといえること(本件鑑定7~12頁)、本件建物の適正継続賃料が本件鑑定のとおり50万8600円(税抜・共益費を含む)と算定され、現行賃料と5万2600円の乖離が生じており、これは現行賃料の1割を超える数値であることからすると、直近合意を不相当とする事情があるといえる。
(4)鑑定時点における適正継続賃料
上記(2)で検討したとおり合理性が認められる本件鑑定の結果によれば、本件建物の鑑定時点における適正継続賃料額は50万8600円(税抜・共益費を含む)である。
(5)差額賃料の支払
弁論の全趣旨によれば、被告は、令和5年7月6日以降も、月額45万3000円(税抜)の現行賃料と3000円の共益費(税抜)の支払を継続してきたものと認められる。そうすると、被告は、本判決確定後、原告に対し、借地借家法32条2項に基づき、差額賃料月額5万2600円(令和5年7月分は日割計算)に支払期日の翌日から1割の割合による利息を付して支払う義務を負う。
2 よって、主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言は相当でないから付さない。
東京地方裁判所民事第7部 裁判官 新谷祐子
以上:5,603文字
Page Top