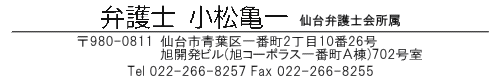| 旧TOP : ホーム > 相続家族 > 遺産分割 > | |
| 令和 1年 5月 7日(火):初稿 |
|
○「相続分譲渡を原則民法第903条1項”贈与”該当しないとした地裁判決紹介」の続きで、その控訴審平成29年6月22日東京高裁判決(家庭の法と裁判19号37頁)全文を紹介します。 ○控訴人が、被控訴人に対し、被相続人が被控訴人に譲渡した相続分も遺留分算定の基礎となる財産に含まれるから、本件遺言によって遺留分を侵害されたと主張して、遺留分減殺請求権に基づき、被控訴人がDから相続した土地建物の共有持分各16分の1につき、遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記手続を、また、既に処分済みの不動産、債権、現金、預貯金及びその他の財産(出資金、簡易生命保険、住宅建物総合保険、電話加入権)と本件預金の各遺留分額の合計金員・遅延損害金の支払を求めていました。 ○原審平成28年12月21日さいたま地裁判決は、相続分の譲渡に伴う個々の相続財産についての共有持分の移転はその後に予定されている遺産分割による権利移転が確定的に生ずるまでの暫定的なものに過ぎず、被相続人が被控訴人へ譲渡した相続分は、被相続人の相続における遺留分算定の基礎となる財産に含まれないので遺留分の侵害はないとの理由で請求を棄却しました。 ○平成29年6月22日東京高裁判決も、相続分の譲渡は,いわば遺産分割に参加する地位と遺産を取得できる枠を譲り渡すものであり,共同相続人が譲り受けた場合,遺産の取得枠が広がるものの,最終的な遺産の帰属は遺産分割協議を待たなければならないのであるから,単純に相続財産の贈与があったものと同視することはできないとの理由で控訴を棄却しました。 ○この一審・控訴審判決は、「相続分譲渡を原則民法第903条1項”贈与”該当とした最高裁判決紹介」記載の通り、平成30年10月19日最高裁判決(家庭の法と裁判19号32頁)で破棄・差し戻しとなっています。その理由は、相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができるというものでした。 ******************************************** 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における新たな請求を棄却する。 3 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 請求1 (1)原判決を取り消す。 (2)被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙物件目録記載1の〔1〕から〔7〕までの土地及び同目録記載2の〔1〕から〔4〕までの建物の持分各16分の1について,平成26年11月27日遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記手続をせよ。 (3)被控訴人は,控訴人に対し,1221万9399円及びこれに対する平成26年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4)仮執行宣言 2 請求2(当審での訴えの変更により新たに追加された請求) (1)原判決を取り消す。 (2)被控訴人は,控訴人に対し,1653万8255円及びこれに対する平成26年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)仮執行宣言 第2 事案の概要 1 控訴人は,D(以下「D」という。)とC(以下「被相続人」という。)夫婦の長女であり,被控訴人は,同夫婦の二男であり,そのほかに三男がおり,また,被控訴人の妻が同夫婦と養子縁組している(なお,長男は早世している。)。埼玉県加須市内に貸家等の不動産を多数所有していたDは,平成20年12月9日に死亡したところ,その遺産分割調停事件の係属中、被相続人及び被控訴人の妻は,被控訴人に対してそれぞれの相続分全部を譲渡し,平成22年12月19日,相続分の割合を控訴人及び三男が各8分の1,被控訴人が4分の3として,Dの遺産を分割する調停が成立した。その間,被相続人は,上記調停成立に先立つ同年8月25日,被相続人の全財産を被控訴人に相続させる旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」という。)をしていたが,その後,平成26年7月24日に死亡した。なお,死亡時における被相続人の財産は,預金35万2557円(以下「本件預金」という。)だけで,債務として未払の介護施設利用料金等36万7937円があった。 2 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被相続人が被控訴人に譲渡した相続分(以下「本件相続分」という。)も遺留分算定の基礎となる財産に含まれるから,本件遺言によって遺留分を侵害されたと主張して,遺留分減殺請求権に基づき,被控訴人がDから相続した原判決別紙物件目録記載の土地建物の共有持分各16分の1につき,遺留分減殺を原因とする持分一部移転登記手続を求めるとともに,既に処分済みの不動産,債権,現金,預貯金及びその他の財産(出資金,簡易生命保険,住宅建物総合保険,電話加入権)並びに本件預金の各遺留分額の合計1221万9399円並びにこれに対する遺留分減殺請求の意思表示をした日の翌日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 3 原審は,被相続人が被控訴人へ譲渡した相続分は,被相続人の相続における遺留分算定の基礎となる財産に含まれないから,控訴人の遺留分の侵害がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却したところ,これを不服とする控訴人が控訴をした。なお,控訴人は,当審において,原審における前記請求(請求1)に加えて,新たに,被控訴人に対して1653万8255円及びこれに対する平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(請求2)を追加し,請求1と請求2は選択的併合請求であるとした。 4 前提事実及び争点とこれに関する当事者双方の主張は,次の5のとおり原判決を補正し,後記6のとおり当審における新たな主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決2頁11行目から5頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 5 原判決の補正 (1)原判決2頁15行目の「及び」の次に「平成18年4月7日にD及び被相続人と養子縁組した」を加える。 (2)原判決3頁11行目から12行目までを次のとおり改める。 「(6)控訴人は,被控訴人に対し,平成26年11月25日付け内容証明郵便をもって,遺留分減殺の意思表示を行い,同郵便は,同月27日,被控訴人に到達した。」 (3)原判決3頁19行目の「理由はない」の次に「(亡Dの遺産総額は2億7483万6519円であるところ,控訴人は,遺産分割調停の結果,このうち2801万円の相続しか受けることしかできず,三男Fは,被控訴人の手心によって6464万円の相続を受けたが,このような差別的状況が生じたのは,本件相続分譲渡の結果,被控訴人が4分の3という圧倒的な相続分を有することになったからにほかならない(なお,控訴人は,その後,亡Dの相続財産の総額が4億5020万6669円であったとの主張をするに至っている。)。)」と付加する。 (4)原判決4頁8行目の「被告が」を「控訴人が」と改める。 (5)原判決5頁5行目の「余地はない」の次に「(なお,相続税評価額を基準とした場合,亡Dの遺産の積極財産は2億4781万4986円であったが,消極財産1億4992万8323円を控除した残額は9788万6663円で,控訴人の法定相続分は1223万5833円であるところ,遺産分割調停の結果,控訴人は2650万8817円の財産を取得している。)」と付加する。 6 当審における当事者の新たな主張 (1)控訴人の主張 ア 被控訴人は,本件相続分の譲渡によって,個々の相続財産を具体的に取得できる権利たる相続分を得たことになるから,本件相続分の価値自体が被控訴人に移転したものとして,これを遺留分減殺の対象になるとも考えられる。そうすると,本件相続分の価値は,Dの遺産総額の2分の1である2億2510万3334円を下ることがなく,これに被相続人の遺産である本件預金を加えると,遺留分算定の基礎財産の評価額は,合計2億2545万5891円(225,103,334+352,557=225,455,891)となるから,控訴人の遺留分の額は3757万5981円(225,455,891×1/6=37,575,981)となり,同額が侵害されている。 イ また,全ての相続財産について民法1040条1項を適用又は準用する構成も考えられ,この場合には,遺産分割協議によって相続時に遡って直接権利移転が生ずるとした民法909条本文の存在を踏まえると,その後の不動産の名義いかんに関わらず,全ての相続財産が遺産分割協議の成立によって処分されたものと評価できるから,民法1040条1項の適用又は準用により,全て価格弁償がなされるべきことになる。そして,この場合にも,上記アと同じく,遺留分侵害額は3757万5981円となる。 ウ したがって,控訴人は,被控訴人に対し,遺留分減殺請求権に基づいて,遺留分侵害額3757万5981円のうち,その一部である1653万8255円及びこれに対する遺留分減殺請求の意思表示をした日の翌日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被控訴人の主張 控訴人は,暫定的な地位にすぎない相続分の譲渡をもって,確定的な権利移転が生じたとみなすに等しく,民法909条本文と整合しない。また,遺留分額の算定について,D及び被相続人のいずれも負債を度外視し,かつ,Dの遺産については将来の未発生の賃料を算入するといった法外な評価方法によるもので相当でない。加えて,民法1040条1項に基づく構成については,遺産分割そのものをもって,「受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡した」と評価する理由はない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,原審と同様に,被相続人が被控訴人へ譲渡した相続分は遺留分算定の基礎となる財産には含まれないというべきであり,本件遺言によって,控訴人の遺留分が侵害されていないので,当審での追加請求を含め,控訴人の請求をいずれも棄却するのが相当であると判断する。その理由は,後記2で控訴人の主張に対する補足説明を加え,後記3で当審における新たな主張に対する判断を示すほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2(原判決5頁11行目から6頁20行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決5頁末行の「権利移転が生ずる」の次に「(最高裁判所平成13年7月10日第三小法廷判決・民集55巻5号955頁参照)」を加える。)。 2 控訴人は,相続人の生計の資本等のために相続財産の一定割合を留保する遺留分制度の趣旨に照らし,相続分が経済的な価値を有する財産であり,その譲渡は生前贈与に当たるから,遺留分算定の基礎となる財産に算入する必要があるとし,遺産分割の遡及効は法技術上の便宜にすぎず,法自体が遡及効を貫徹していないし,最高裁判所の判例(平成17年9月8日第一小法廷判決・民集59巻7号1931頁)も,遺産分割前に発生した事実が遺産分割協議の成立によって変更されないことを示している等と主張する。 相続分の譲渡において,その譲渡の対象となる相続分とは,被相続人の積極財産だけでなく,消極財産を含めた包括的な財産全体に対して共同相続人が有する割合的な持分であること,共同相続人間で相続分が譲渡されたときには,もともと当該共同相続人が有する固有の持分に,譲り受けた他の共同相続人の持分を加えて,増加した相続分の割合をもって遺産分割に参加することになること,遺産分割がなされるまでの間は,共同相続人がその持分割合によって暫定的に相続財産を共有する関係にあるが,遺産分割協議が成立すると,その結果に従って相続開始の時に遡って被相続人からの直接的な権利移転が生ずることは,上記で引用する原判決が説示するとおりである。 このように,相続分の譲渡によって,遺産分割が行われるまでは,潜在的に保有している相続財産の持分が移転するという形にはなるが,それはあくまで暫定的なものであって,最終的に遺産分割が確定すれば,その遡及効によって,相続分の譲渡人は,相続開始時から被相続人の相続財産を取得しなかったことになるから,相続分の譲渡人とこれを譲り受ける者との間に,相続財産の贈与があったとは観念できないものである。 この点,控訴人は,相続分の譲渡では遺産分割の遡及効が制限され,遺産分割前の譲渡事実を否定できないと主張する。 しかしながら,民法909条但書が定めるとおり,遡及効の制限は,第三者との取引の安全を保護するためのものであるのに対し,控訴人が主張する遡及効の制限は,共同相続人間での相続分の譲渡について,遺産分割協議成立にもかかわらず,なお共同相続人間の贈与と同様の効果を認めようとするもので,第三者との取引の安全が問題とされているものではないから,遡及効が制限される理由はないというべきである。 控訴人が指摘する上記判例は,相続開始から遺産分割までの間に,共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属とこれに及ぼす遺産分割の遡及効の有無が問題となり,遺産から生じた果実たる賃料債権は,遺産とは別個の財産であって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するもので,遺産分割の影響を受けない旨を判示したものであり,遺産の帰属そのものが問題となっている本件とは事案を異にしており,控訴人の上記主張の根拠とはならない。 また,控訴人は,相続分が経済的な価値を有する財産であり,その譲渡は生前贈与に当たるとも主張する。 しかしながら,相続分の譲渡によって,包括的な相続財産の持分とともに,譲渡人が有していた遺産に関わる法的地位も承継されることになり,譲渡人に特別受益があってその法定相続分を超過している場合には,譲り受けた相続分の取得額が零になることもあるから,相続分の譲渡が必ずしも経済的な利益の増加をもたらすわけではない。民法1029条及び1030条に定める贈与については,全ての無償処分を意味し,債務免除や無償の人的物的担保の供与を含むなど,実質的な見地からの経済的な利益の供与まで広く含んでいると解されているが,相続分については,積極財産及び消極財産や特別受益,寄与分等の調整要素を含んだ包括的な地位であるから,その利益性の判断については総合的な評価を要するものであって,直ちにその経済的な利益を測ることはできない。 そして,遺産分割は,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行い(民法906条),共同相続人の協議によって,定められた相続分とは異なる内容の遺産分割を取り決めることも許され,最終的にどれだけの遺産を取得できるかは,遺産分割協議を経て決せられるものであって,結局のところ,相続分の譲渡は,いわば遺産分割に参加する地位と遺産を取得できる枠を譲り渡すものであり,共同相続人が譲り受けた場合,遺産の取得枠が広がるものの,最終的な遺産の帰属は遺産分割協議を待たなければならないのであるから,単純に相続財産の贈与があったものと同視することはできない。 現に,本件でも,遺産分割調停の内容に関する双方の主張は,いずれも,相続分譲渡の結果に基づく相続分(被控訴人4分の3,控訴人及び三男が各8分の1)とは大幅に異なる取得額で遺産分割調停が成立したというものであり(例えば,証拠(甲11,乙6)と弁論の全趣旨によれば,相続税申告時における亡Dの遺産総額は,積極財産から消極財産を除くと1億0878万5216円であるから,控訴人の法定相続分8分の1に相当する金額は1359万8152円であるのに対し,控訴人の取得した不動産の評価額は2346万0817円で,そのほかに代償金も取得したことが認められる(なお,上記消極財産は,被控訴人において取得したと被控訴人は主張している。)。),このような遺産分割調停の結果を無視して,被相続人から被控訴人に対し,亡Dの遺産の2分の1に相当する贈与があったものとして遺留分減殺請求を認めるなどということが不合理であることは明らかである。 したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。 3 控訴人の当審における新たな請求は,相続分の譲渡が遺留分算定の基礎となる財産に含まれることを前提とするものであり,その前提が採用できないことは既に説示したとおりであるから,上記請求は前提を欠いており,失当というべきである。 したがって,控訴人の当審における新たな請求は理由がない。 4 以上のとおり,本件控訴は理由がなく,また,控訴人の当審における新たな請求も理由がないから,いずれもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第19民事部 裁判長裁判官 都築政則 裁判官 石垣陽介 裁判官 野本淑子 以上:7,022文字
|