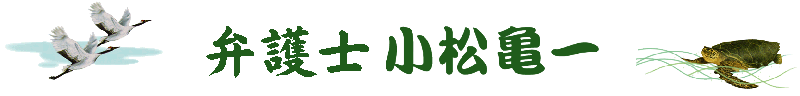○本件建物の区分所有者である上告人が、上階からの漏水事故が発生したと主張して、上階に居住する第一審被告Pと本件建物の区分所有者全員で構成され本件建物を管理する組合である被上告人に対し、本件各調査及び本件各補修を行うよう求め、また債務不履行、不法行為又は工作物責任に基づく損害賠償請求として、補修費用約1400万円の支払を求めました。
○第一審東京地裁は、本件事故の原因は、本件バルコニーに面した北側外壁のコンクリート躯体部分に隙間ないし亀裂が生じていたことによるもので、この部分は、本件建物の区分所有者全員が占有しているものであり、その部分に存する隙間ないし亀裂を放置している以上、占有者である本件建物の区分所有者全員に保存の瑕疵があり、原告は、本件事故に関し、被告組合に対して損害賠償請求をすることができるとして、被告らに1047万円の支払を命じました。
○双方がそれぞれ控訴し、控訴審東京高裁は、上告人の請求は、一審被告Pに対しては一部理由があるが、上告人による被上告人組合の管理義務違反を理由とする債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないとして、原判決を変更しました。
○そこで、上告人が上告したところ、民法717条1項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して上記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにあると解されるところ、被上告人組合は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるとし、これと異なる見解の下に、被上告人組合は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないとした控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、控訴審判決中、上告人の被上告人組合に対する損害賠償請求に関する部分を破棄し、当該部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻した令和8年1月22日最高裁判決(裁判所ウェブサイト)全文を紹介します。
*********************************************
主 文
1 原判決中、上告人の被上告人に対する損害賠償請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人○○○○○の上告受理申立て理由について
1 本件は、上告人が、区分所有建物の共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって損害を被ったと主張して,同区分所有建物の管理組合であり、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)3条前段所定の団体(以下「区分所有者の団体」という。)である被上告人に対し、民法717条1項本文に基づく損害賠償を求めるなどする事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人は、東京都練馬区に所在する1棟の区分所有建物(平成2年5月に新築され、総戸数27戸のもの。以下「本件区分所有建物」という。)の区分所有者の団体である。
上告人は、本件区分所有建物の専有部分である203号室の共有者である。
(2)被上告人の規約には、共用部分の管理については、被上告人がその責任と負担においてこれを行うものとする旨の定め(20条)、被上告人は、被上告人が管理する共用部分の保全及び保守並びに修繕を行う旨の定め(31条)がある。
(3)本件区分所有建物においては、平成25年10月から平成27年3月にかけて、4回にわたって、外壁コンクリート躯体部分及び床下スラブ部分(以下「本件外壁部分等」という。)の亀裂等により、203号室への漏水事故が発生した。上記亀裂等は、工作物の設置又は保存の瑕疵に当たり、上記亀裂等が生じた本件外壁部分等は、本件区分所有建物の共用部分に当たる。
3 原審は、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないと判断して、上告人の被上告人に対する同項本文に基づく損害賠償請求を棄却した。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)民法717条1項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して上記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにあると解される。
区分所有法によると、区分所有者は、全員で、区分所有建物等の管理を行うための団体を構成し(3条前段)、区分所有建物の共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するとされている(18条1項)。これら区分所有法の規定に照らすと、区分所有建物の共用部分については、基本的に、区分所有者の団体がこれを支配管理して通常有すべき安全性を確保していくことが予定されているものというべきである(このことは、区分所有法25条及び26条に管理者の選任及び権限等についての定めがあるからといって、左右されるものではない。)。そうすると、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理してその設置又は保存の瑕疵による損害の発生を防止すべき地位にあるということができる。
また、区分所有者の団体は、区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のための費用を徴収しているのが通例であるところ(区分所有法19条参照)、共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合には、区分所有者の団体の財産からその賠償をすることが、区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護にも資するものといえる。
以上によれば、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるというべきである。
(2)そして、本件において特段の事情はうかがわれないから、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる。
5 以上と異なる見解の下に、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中、上告人の被上告人に対する損害賠償請求に関する部分は破棄を免れない。そして、損害額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
なお、その余の請求に関する上告については、上告人が上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないから、これを却下することとする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡正晶 裁判官 安浪亮介 裁判官 堺徹 裁判官 宮川美津子 裁判官 中村愼)
以上:2,891文字
Page Top